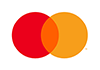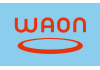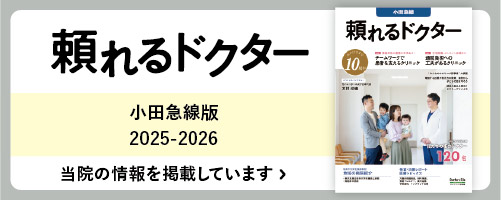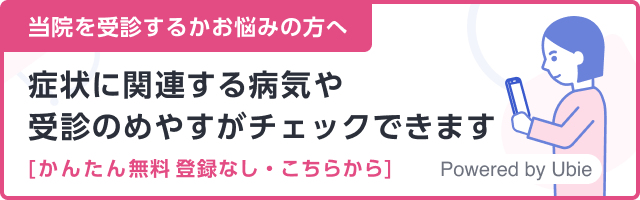高尿酸血症(痛風)とは

尿酸は血液中に含まれているもので、何かしらの原因でこれが増えている状態を高尿酸血症と言います。尿酸は水にとけにくく、これが過多になると針状の結晶をした尿酸塩として血液中に存在します。そして関節に溜まってしまうと、激痛を伴う炎症発作(とくに足の親指の付け根付近)が発症します。これが痛風です。
なお高尿酸血症は痛風の症状が起きるまでは自覚症状が現れることはほぼありません。ただ発症の有無に関しては血液検査で確認することもできます。同検査をした際に血清尿酸値という数値が7.0mg/dL以上と判定されると高尿酸血症と診断され、この数値が確認された場合、痛風がいつ発症してもおかしくない状態です。また、痛風の症状が現れなかったとしても、痛風結節、尿路結石、腎障害、脳血管障害、心疾患といった合併症を発症するリスクを高くさせてしまうので要注意です。
発症の原因
先にも述べたように高尿酸血症は血液中において尿酸が過多になることで発症しますが、増えてしまう原因としては、先天的な代謝異常、造血器疾患、尿酸が排出されにくい体質といったことが挙げられます。しかし、そのほかにも尿酸のもととなるプリン体を多く含む食品(レバー類、干し椎茸、魚卵類、えび、かつお、いわしなど一部の魚介類)を必要以上に取っている、多量の飲酒、過度な無酸素運動などによって引き起こされることもありますので、日頃からの生活習慣を見直していく必要があります。
治療について
尿酸値を下げるための治療と痛風で生じる炎症発作を抑えるための治療があります。
尿酸値を下げる治療では、まず生活習慣の改善(食事療法、運動療法)を行っていきます。食事療法では、野菜、海藻、きのこ、豆類などを取るようにするほか、減塩にも努めます。またプリン体を多く含む食品は避け、お酒を飲まれる方は節酒します。さらに水分を多く摂取し、体内の尿酸を尿と一緒に排出していくようにします。また運動も尿酸値を下げるのに有効です。有酸素運動(1回30分程度のウォーキング 等)でも充分ですが、継続的に行う必要があります。運動メニューについてはご相談ください。またこれらと併行して、尿酸値を下げる治療薬(尿酸の生成を減らす効果がある薬、尿酸の排出を増やす薬)も使用していきます。
一方、痛風による炎症発作の治療ですが、こちらは薬物療法が中心です。用いられるのは、NSAIDs、ステロイド、コルヒチンなどです。これらの治療で、痛みや腫れといった炎症発作が抑えられるようになったら、尿酸値を下げる治療が開始されます。